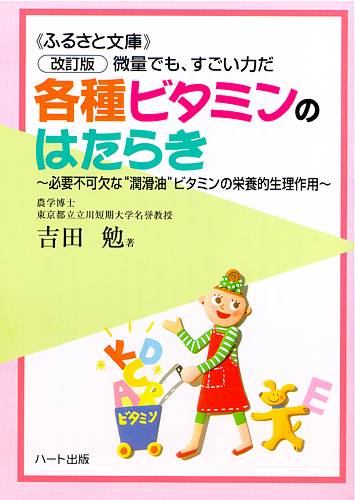
レチノールとベータカロテン
ビタミンA作用をもつ物質は大別して二種類あります。一つはAの本体である動物性食品由来のレチノール(ビタミンA の化学名)。もう一つが体内でビタミンAに変化する植物性食品由来の「プロビタミンA(α、β、γカロテンなど)」です。
なおカロテンとは、以前はカロチンと言っていた物質です。
プロビタミンAの中で、ビタミンAに変化する量が最も多いのが「βカロテン」です。βカロテンはレチノールが二つくっついた形をしていて、小腸で吸収される際に約半分がレチノールに変化し、その吸収率はレチノールの約三分の一です。
基本的な働き/目と皮膚の正常化
ビタミンAは、目の機能を正常に保つうえで不可欠の栄養素です。
私たちの目は、通常、薄暗いところでもモノを判別でき、急に暗い場所へ入ってもすぐに順応する能力があります。薄明視、暗調能と呼ばれる能力ですが、これらは網膜(桿体細胞)中にあるロドプシンという“視物質”の働きで調節されています。
このロドプシンを構成している主成分がビタミンAなのです。
ビタミンAは、上皮細胞を丈夫に保つうえでも欠かせません。
上皮細胞とは、皮膚をはじめ、呼吸器や消化管を覆う粘膜のことです。外界と直に接する部分なので、常時、有害物質や細菌・ウィルスなどの攻撃にさらされていますが、ビタミンAが十分にあると、粘膜の保護に働く粘液の分泌が促されてそれらの攻撃をシャットアウトできます。
欠乏症/夜盲症、皮膚粘膜の角化
ビタミンAが欠乏すると、夜盲症(トリ目)、眼球乾燥症(ドライアイ)、皮膚・粘膜の角化などが生じてきます。
また、上皮細胞の機能が低下して病原菌に冒されやすくなるほか、体の成長や発育も阻害されます。動物実験では、生殖機能に支障が出ることも報告されています。
上手な取り方/油と一緒にとる
ビタミンAの栄養所要量は、成人男性で2000IU(600μgRE )、成人女性で1800IU(540μgRE)です。 とは「レチノール当量」ということで、ビタミンA に相当する量のことです。レチノールはどのような食べ方でもよく体内に吸収されますが、βカロテンは油と一緒にとらないとあまり吸収されません。βカロテンの豊富な緑黄色野菜をとるときは、油で調理するか油を含む食品と一緒にとることが大切です。
過剰症/レチノールの取りすぎは危険
レチノールの取りすぎは過剰症を引き起こします。急性症状としては頭痛、めまい吐き気、慢性症状では頭痛のほか、皮膚の異常や肝障害を起こす例もあるようです。 アメリカの疫学調査では、毎日15000IU(4500μgRE)以上のビタミンAをとり続けた妊婦は、先天異常の乳児が生まれる確率が通常の三・五倍も高いことが報告されています(一九九六年一月二0日刊 日本経済新聞の紙面より)。このことなどから、ビタミンAの許容上限摂取量は5000IU(1500μgRE)になっています。
なお、βカロテンの形でとった場合は、過剰症の心配はないとされています。βカロテンのレチノールへの変換率は約50%と低く、平均体内吸収率がレチノールの三分の一程度なのも影響しているようです。
| ビタミンAを含む食品(μgRE/100g当たり) | |||
| レチノールの多いもの | カロテンの多いもの | ||
| 《魚類》 | 《野菜》 | ||
| あんこう肝 | 8300 | しそ(葉) | 1800 |
| やつめウナギ | 8200 | にんじん | 1500 |
| うなぎ(肝) | 4400 | パセリ | 1200 |
| うなぎ蒲焼き | 1500 | あしたば | 880 |
| ほたるいか | 1500 | しゅんぎく | 750 |
| 銀だら | 1100 | ほうれん草 | 700 |
| あなご | 500 | だいこん葉 | 650 |
| 《肉類》 | にら | 590 | |
| 鶏レバー | 14000 | おかひじき | 550 |
| 豚レバー | 13000 | 糸みつば | 540 |
| 牛レバー | 1100 | こまつな | 520 |
| 《卵類》 | かぶ葉 | 470 | |
| 卵黄 | 480 | しそ(実) | 440 |
| 鶏卵(全卵) | 150 | 《藻類》 | |
| 《乳製品》 | 干しあまのり | 7200 | |
| チェダーチーズ | 350 | 焼きのり | 4600 |
| プロセスチーズ | 280 | あおのり | 2900 |
| クリームチーズ | 270 | わかめ(素干し) | 1300 |
| 《油脂類》 | 《茶》 | ||
| マーガリン(上級) | 1800 | せん茶 | 2200 |
| バター(無塩) | 800 | 抹茶 | 480 |
| マーガリン(標準) | 48 | ||
